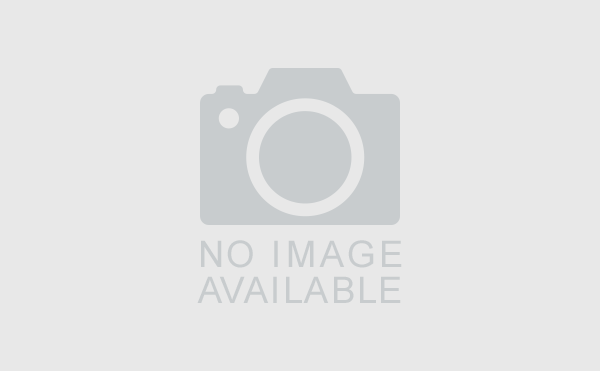仏が人になって下さる
織田隆深
先月、六月十九日に博多で久しぶりに法話会を開いた。その前に山口県萩に寄った。吉田松陰先生を祀る神社や明治の元勲を輩出した松下村塾を見学した。資料館も充実しており、松陰先生の事跡を年代順に資料も交え生涯をわかりやすく展示していた。生涯と云っても三十歳で刑死した。短い生涯ではあるが、後に、松陰先生の意をくんだ人材は、明治の基礎を作った。高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、木戸孝允、山形有朋、山田顕義等、途中で斃れた人も多数いた。皆十代末から三十歳代である。松陰が直接教えたのは僅か一年半の短い期間だったが、多くの志のある人間を育てた。
資料館には、松陰先生の名言が掲げられていた。
「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に、夢なき者に成功なし」
「自分の価値観で人を責めない。 一つの失敗で全て否定しない。 長所を見て短所を見ない。 心を見て結果を見ない。 そうすれば人は必ず集まってくる。」
「誠は天の道なり、誠を思うは人の道なり、至誠にして動かざるものは、未だ之あらざるなり」(『孟子』を引用)
「かくすればかくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂」
「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも、留め置かまし大和魂」
一言で言えば、松陰先生は至誠の人である。これに比し、現在の政治家、官僚たちはどうしようもない連中ばかりである。利権で働き国を売る政治家や高級官僚ばかり目立つ。現状を見る時、松陰先生の「至誠」の言行が痛いくらい心につきささる。先人たちは何の為に命を捧げたのかと。至誠は仏教でいうなら菩提心であろう。命より大事なものが誠である。だから命より大事なものを成し遂げる為に命は大切なのである。ただ長生きするだけの命ではない。
前号で観音菩薩が三十三身に変化し、われら一切衆生を済度することを説いた。仏(如来)と我等衆生との関係を述べたい。
我等仏教徒として先ず守るべきことは仏法僧の三宝に帰依することである。仏は仏陀(如来)のことで迷いから目覚めた人、悟りを開いた人である。
仏の持つ十種の尊称、仏が具えた福徳を表わす「仏の十号」がある。①如来(如〔法〕より来生する) ②応供(供養を受ける資格のある者。阿羅漢) ③正遍知(一切を知る者) ④明行足(智慧と修行をそなえた者) ⑤善逝(よく悟りに到達した者) ⑥世間解(世間の有情非情のことを巧みに理解する者) ⑦無上士(衆生の中でこの上なくすぐれている者) ⑧調御丈夫(さまざまな言説によって巧みに人を導く者) ⑨天人師(神と人の師匠) ⑩仏・世尊(世のあらゆる人から尊敬される者)
これらの十号の中で、よく使われる名称は仏・世尊と如来であろう。如来を除けば、あとは釈尊個人を讃える尊称といってもいい。「如来」だけは、釈尊も含むが釈尊以外のたくさんの仏を意味する。
如は悟りの世界を意味し、法ともいうし、如如、一如、真如、法如等、種々の言葉で表現する。如来とは如(悟り)から来る「一如来生」というように、如(覚りの世界)から、我ら衆生を救う為に、具体的に人間の形を取って表われる。覚りの姿を如来という具体的な姿で表現する。人類で初めて覚りを開かれたのは釈尊なので、仏画や仏像は釈尊の姿で表わす。応身仏といえば、釈尊のことである。人間の身体に応じて現われた仏陀という意味である。大乗仏教が生まれる紀元前後までは、仏と云えば釈尊だけだった。大乗仏教が現れると釈尊以外の仏、菩薩が次々と現れてくる。釈尊が悟った内容は法(真実の道理)の世界である。この法は色も形もない、言葉で表すこともできない不可説、不可得の世界で、敢えて表現するなら虚空の如き世界である。故に釈尊が法を悟るまでは、法の存在すらわからなかった。釈尊が法の世界を発見されたので、釈尊のことを仏陀と呼んだ。つまり、法を悟った方を仏陀と呼ばれたのである。
釈尊のように修行されて仏陀に成られた方が他におられないかと云えばそうでもない。
最初は釈尊しか仏陀はおられなかったが、釈尊が最初に御自身が悟られた際に、この真実の法を多くの人々に教え苦悩から救わなければならないと決心された。しかし、一般の人々は従来のバラモン教の神々を信じていたので、悟った法の内容をすぐ理解できないだろうと、釈尊は一瞬躊躇された。しかし、成道前まで一緒に修行してきた五人の修行者なら理解してくれるのではないかと、先ず彼らに悟った内容を説かれた。その中の一人、アンニャコンダンニャという行者が釈尊の説法を聞いて悟りを開かれた。もう一人の仏陀が誕生したのである。
もう一人の仏陀が現れることにより、釈尊の悟りが証明されたのである。そして、他の四人も次々と悟られ、五人の仏陀が生まれたのである。諸仏が証明して、初めて仏陀の悟りが間違いないことが証された。仏教は証明、自覚の教えで一方的な思い込みにならないよう諸仏の証明讃歎が必要な宗教である。各宗旨の祖師方も文章を書く時は必ず経証を引用し、これは自分の独断でないことを仏説を引いて証明する。釈尊入滅後、五百年は、生きた仏陀は消えて無くなったようなものである。ただし、釈尊が入滅前の説法で「私も因縁によって生きているので、まもなく死を迎える。その時にあわてないよう、わが亡き後には、法を拠り所にしなさい、そして、自分自身を信じなさい」と、有名な「自灯明・法灯明」の教えを遺された。法(仏)が我を已に信じているということを法灯明、我が法を信じることを自灯明という。法と我は不可分の関係にあることを説いている。
そして釈尊滅後、五百年を経て、大衆部をはじめ、多くの僧侶方がようやく、釈尊が悟られた法こそ、仏陀の生まれる根源であることにあらためて注目した。しかも、法には我等をして悟らせる力があることに気付かれた。それは慈悲心である。後に言う本願力廻向とか、加持力がこれである。法を具現化した姿が仏・菩薩である。人が仏に成る道と、法が仏になり、更に仏が人になる道があることに気づかれた。釈尊が涅槃に入られても何ら悲しむことはない、無仏ではない。法から無尽に仏が現われて、仏が我になって我を救って下さるではないかと、今迄とは真逆の成仏道があると。それまでは法は真理としてじっと動かず、人間のみが法に近づいて法の世界を開かなければと思っていた。しかし、法は常に我らを成仏させる為に働いていることに気づいたのである。
今までの成仏道は出家しか歩むことのできない小さな道、小さな教えであるが、法という大道は出家、在家共に歩むことのできる「遊証の平路、還寂の大道」であると。
更に、大事なことは、仏と我との関係である。覚者のことを仏と云い、迷える凡夫を衆生というが、果たして我と仏はまるっきり別の存在であろうか。
我等の本質は、仏から見ると皆平等である。ただ我らは自分の深い心の底に仏の心が流れていることを知らないで迷っている。何とかこのことを知らせなければならないと、法は大慈悲心を起された。この大慈悲心が具体的に我らを救おうとされる願い、祈りなのである。故に仏は我々が迷っていても、我々の心の奥底は仏心と等しいもの(仏性)があると信じておられる。信じておられるから、何とか救わなければならないと慈悲心がわいてくるのである。
慈悲心とは、単なるあわれみ、可愛そうだという同情ではない。仏と我の関係は、切っても切れない関係にある。我は仏の一部である。一部であるが、全体(仏・法)に連なっている。『華厳経』では「一即多、多即一」と表現している。一を機、有限と見、多を法、無限と見るなら、機法一体、我と仏は二而不二の関係である。
仏なくして我もないし、我なくして仏もない。そういう関係であるから、大慈悲心がわいてくるのである。親子関係よりも、もっと深い不可分の関係である。我らの悲しみそのものが仏の悲しみであり、また喜びそのものが仏の喜びである。死ぬのも生きるも仏と一緒である。
我々が本当に迷っていることに気がつけば、迷いは消えていく。迷いの本性を照らして迷いの根源教えているのが仏の智慧であり、それを行動に移しているのが、慈悲心である。このように仏は我との関係を深く知り、信じていることがわかれば、我々は仏が已に我々を深く信じていることを、ありがたくいただくことができる。
仏と我は越えられない距離があるように見えるが、大師が「悟れるものは大覚と号し、迷えるものは衆生と名づく」というように、悟るか迷うかの違いで、本体は変らないと説かれている。
密教的に表現すれば、仏も六大、我も六大によって成り立っている。本体は同じである。このことに気づくなら、迷悟は紙一重である。大師は、「それ仏法はるかにあらず、心中にしてすなわち近し。真如外にあらず、身を棄てていずくんか求めん。迷悟われに在れば発心すればすなわち到る。明暗他にあらざれば、信修すれば、たちまちに證す」(『般若心経秘鍵』)と書いている。
仏は我を信じ、我は仏を信じる。「心仏衆生是三無差別」という言葉があるように、仏・我・衆生は平等である。成仏といっても別の存在にあるわけではない。もともとある本性(仏性)に目覚めること、帰ることを成仏という。
そういうわけで、人が仏になるというより、仏が人になって下さる事実を信じ知ること、この道理は即身成仏に通じている。