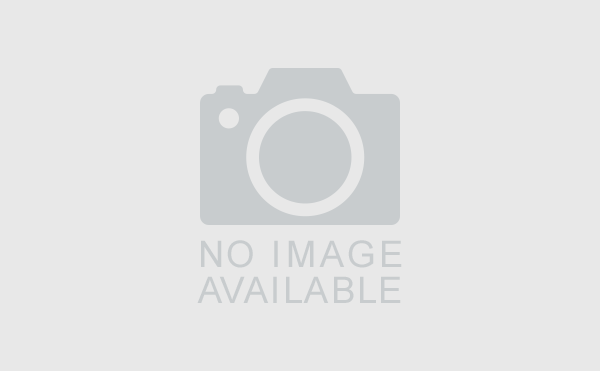氷と水の如くにて
織田隆深
今年も暑い夏がやってきました。世界でも国によっては四十、五十度に近い所もあり、四十度以上になると、アスファルトが溶けたり、外での労働にもさしつかえるようです。欧州でも日本の高性能のエアコンが飛ぶように売れています。
また、日本で発明された空調服が、国内はもちろん世界でも、炎天下で働く人には、必需品になっております。最近、海外から来る観光客も土産で買っていくので品薄とのことです。
猛暑の夏になると、いつも思い出すのは、親鸞聖人の「高僧和讃(曇鸞讃)」の一節です。(※引用は『真宗聖典』による)
無碍光の利益より
威徳広大の信をえて
かならず煩悩のこおりとけ
すなはち菩提のみずとなる
罪障功徳の体となる
こおりとみずのごとくにて
こおりおおきにみずおおし
さわりおおきに徳おおし
名号不思議の海水は
逆謗の屍骸もとどまらず
衆悪の万川帰しぬれば
功徳のうしおに一味なり
尽十方無碍光の
大悲大願の海水に
煩悩の衆流帰しぬれば
智慧のうしおに一味なり
また白隠禅師の「坐禅和讃」にも
衆生本来仏なり
水と氷のごとくにて
水を離れて氷なく
衆生の外に仏なし
衆生近きを知らずして
遠く求むるはかなさよ
たとえば水の中にいて
渇を叫ぶがごとくなり
その他にも氷と水の喩えで、唐代天台国清寺にいたとされる伝説の僧寒山の詩の一節(「欲識生死譬」)
生死の譬えを識らんと欲すれば
且く氷と水とを将って比えん
水結ぼるれば即ち氷と成り
氷とくれば返りて水と成る
已に死すれば必ず応に生まるべく
出生すれば還た復た死す
氷と水と相傷なわず
生と死と還た双つながら美し
氷が溶けても水が増えるわけではありません。氷は水よりも体積が大きいため、溶けると体積が減り元の水と同じ体積になります。
このように、氷と水の関係は二にして不二のものです。これを如来と衆生の関係に譬えたのです。
氷と水の比喩は「煩悩と菩提」、「衆生と仏」、「生と死」のように、相反するものが、深い意味では、一つものであることを云っている。
特に親鸞聖人の和讃では、氷は煩悩、水は菩提(悟り)の意味を明確に述べていると思う。
煩悩は、人間の身心を苦しめ悩ます原因となり、理想の境地を実現する妨げとなる心理作用、精神状態のことです。
仏教の学問では、一切有部の五位七十五法で、迷いの世界を分類し、更に唯識論では、五位百法で、心というものを非常に詳しく分析しています。
特に、三毒(貪・瞋・痴)の煩悩、四大煩悩(我癡、我見、我慢、我愛)、唯識の学問として、また煩悩障・所知障(正智をさまたげる)等がある。
大煩悩(根本煩悩)として貪・瞋・痴・無明・慢・見があり、小煩悩(随煩悩)として忿・恨・覆・悩・等がある。
1、忿(ふん)…「瞋」から派生する、具体的な激しい怒り。
2、恨(こん)…「瞋」から派生する、恨み・怨念。
3、覆(ふく)…自分の過ちをごまかし隠す。「貪」「痴」から派生する。
4、悩(のう)…悩み苦しんで、周囲をも悩ます。「瞋」から派生する。
5、嫉(しつ)…嫉妬して心が穏やかでないこと。「瞋」から派生する。
6、慳(けん)…財産や教えを他人に渡すまいとする。「貪」から派生する。
7、誑(おう)…本心を偽って他人を欺くこと。「貪」「癡」から派生する。
8、諂(てん)…人からよく思われようとする。「貪」「癡」から派生する。
9、憍(きょう)…おごり、うぬぼれること。「貪」から派生する。
10、害…他の者に優しい気持ちがなく傷つける。「瞋」から派生する。
11、無慚…善を拒絶し、悪い行いを増大させる心のはたらき。
12、無愧…悪を尊び、悪い行いを増大させる心のはたらき。
13、惛沈(こんぢん)…心が暗く落ち込む。鬱の状態。
14、懈怠(けだい)…「精進」の反対。悪を断ち善を修するのにおっくうなこと。
17、放逸…「不放逸」の反対。勝手気儘に振る舞う心のはたらき。
18、失念…記憶を失うこと。このことから心の集中力を喪失する。
19、散乱…心が集中できずに散乱する。
20、不正知…誤った理解・知識。これにより善を修することができない。
煩悩は普段は、眼・耳・鼻・舌・身・意の六識と、更に寝ている時も気絶している時も働いている深層意識というものがあります。本能といっていい深い所に、自分中心の心の働きがあります、そういう意味では、とても深い潜在意識の世界です。
故に、この煩悩はなかなか根が深い。軽い煩悩もありますが、大煩悩ともなると本能的な心の働きなので、なかなか目覚めることができません。道理から言えば、煩悩という不変の実体があるわけではありません。いろんな条件によって偶々わいてきた心であり、永遠に自分の心に居座るわけではない。条件が変ると消えていくので、客塵煩悩とも呼ばれています。外から飛んでくっついた塵みたいなもので、風が吹けば、消えてしまうようなものであると。
そういう煩悩もあるかもしれませんが、我々が常に覆われて身動きできない煩悩が問題なのです。確かに煩悩と言っても道理から云えば実体のない根無し草のようなもので、条件が変ればサーッと居なくなる存在でしょう。しかし我々が常に悩まされている煩悩は、そんな生やさしいものではありません。末那識という深層意識がかかわっているので、なかなかこれを自覚することが難しいのです。この末那識が常に依所をしている、もっと広く深い個を越えた公の心である阿頼耶識があります。この阿頼耶識という仏の光に照らされてはじめて我が身の現実(現行)に目が覚めるのです。
煩悩ばかり強調したようですが、善い心もあります。信・慚・愧・無貪・無瞋・無痴等の善心所もあります。
1、信…清らかな心で事実を素直に理解する。三宝(仏・法・僧)への憧憬。
2、慚(ざん)…善いことがらを尊び、悪い行いを行なわないようにする。
3、愧(き)…悪いことがらを拒絶し、悪い行いを行なわないようにする。
4、無貪(むとん)…迷いの存在である自己や、自己の周囲の世界に執着しない。
5、無瞋(むしん)…自己中心的な気持ちから起こる怒り・嫌悪を持たない。
6、無癡(むち)…真実のあり方について正しく明らかに知る。
7、精進…悪を断じ善を行うことに勇敢なこと。「勤」ともいう。
8、軽安…心身が軽やかでのびのびしていること。
9、不放逸…精進・無貪・無瞋・無癡がよく善を修していること。
10、行捨…精進・無貪・無瞋・無癡が心の平安をもたらしていること。
11、不害…無瞋の心から他者の心身に危害を与えず慈愛の心を持つこと。
煩悩に対して、本質を看破すれば、たちまちに消え去ると見る立場と、一方、確かに道理から云えば実体の無い、幻の如きはかない存在だが、末那識という深層意識に覆われている煩悩は世界の誰よりも自分のことを愛し、心配し、執着し、いつも応援する心なので、なかなか煩悩の本性を見極めることができないのです。
煩悩に悩んで困っている弟子唯円が、恐る恐る師匠に「念仏しても踊躍歓喜の心がわいてこないのは、どうしてでしょうか」という問いに、親鸞聖人は、「実は私もそうなのだ」と答えられました。よくよく考えてみれば、天におどり地におどるほどの喜びがわかないのは煩悩の働きである。
仏は、かねてからこのことを知っておられ、他力の悲願は煩悩具足で苦しみ悩む凡夫の為に発しておられるのだから、いよいよたのもしく思われるのです。
また、浄土に行きたいという心がおこらず、ちょっとでも病気になると、このまま死ぬのではないかと心細く思うのも煩悩の働きです。
「久遠劫より今まで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだ生まれざる安養の浄土は恋しからず候こと、まことによくよく煩悩の興盛に候にこそ。なごりおしく思えども、娑婆の縁つきて、ちからなくして終わるときに、かの土へは参るべきなり」 (『歎異抄』第九条より)
これは私が、信心に行きづまった時、いつも読み直す文章です。
氷多きに水多し、煩悩が多い程、水つまり悟りも多い。煩悩が多いからと嘆くことはない。それにも増して悟り(大慈悲心)がわれを包んで下さる。煩悩が深い程、菩提(悟り)も深いのだ。煩悩が返って菩提を証明してくれる。
煩悩の正体に気がつけば、煩悩がそのまま菩提となる事実を教えてくださる。「煩悩即菩提、生死即涅槃」という表現が矛盾なく受け入れられると思います。
何と頼もしくもありがたい大慈悲ではないでしょうか。一見相反する煩悩(迷い)と菩提(悟り)が不可分の関係であることを示しているのです。
そういう意味で、密教経典『理趣経』の十七清浄句の、「愛縛清浄句是菩薩位」等、煩悩そのものが菩薩の位にあるという深意は、煩悩というものを深く知らなければ危険な解釈に陥ると思います。
我等衆生に代って発した、菩薩の「煩悩無尽誓願断」という願いに、ただただありがとうございますと感謝するしかありません。