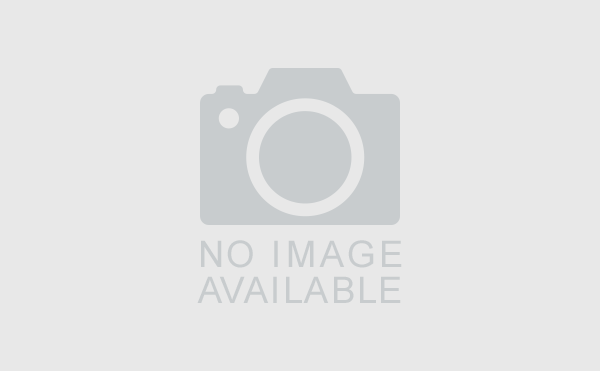転迷開悟
仏教の目標は、自分以外にある霊的存在として仏を信じることではない。成仏することである。
成仏、仏になるということは、真実の道理に照らされ、迷いから目覚めることである。
仏敎は仏の道理(教)を説き、同時に成仏する実践道を説く。
釈尊は、先ず四諦を説かれた。この世は「一切皆苦」である。なぜ苦しむのかという人生の大問題について、四つの諦(真理)で表現した。先ず、苦から目を離さず、苦の現状をありのままに正しく観なさいと苦諦を説かれた。この苦諦が分かれば一切が分かるが、更に詳しく、苦しむ原因となるのは何か、苦がなぜ起こるか、その原因を集諦として説かれた。そして苦が消滅した状態はどのような心境になるか、つまり苦から開放された悟りの状態である滅諦を説かれた。そして滅諦に至る実践道である道諦を説かれた。
この四諦は、仏教とは何かを極めてシンプルにまとめた内容である。四苦八苦に代表されるように「生・老・病・死」「愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五蘊盛苦」のように苦に満ちている。前者は肉体を持ったが故の苦しみ、後者は人間関係の苦痛である。
苦を感ずるのは心と身体であるが、身体は病気とか怪我の時、確かに苦痛を感ずるが、日常圧倒的に苦痛を感ずるのは心である。
この世はもちろん人間も六大(地大・水大・火大・風大・空大・識大)によって成り立っている。前五大は色も形もある肉体にかかわる。最後の識大は形のない心の問題にかかわる。心は決まった形がない。具体的につかむことができない。縁に応じて生じたり、縁により消滅する。不可得・不可説の存在で虚空の如しとしか表現できない。
心は不可思議なもので善も悪も、利己・利他・愛憎・慈悲、あらゆるものを考え、それを実行する。身体は心に従って働く。自身をはじめ、この世のあらゆることを心は動かしている。身体は生まれると同時に正確に心臓を動かし、各内臓を働かせ、呼吸、消化、排泄し、体温を保ち、年齢に応じて生理作用を死ぬまで続ける。これも心の働きである。表面上の眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識の六識はもちろん、寝ている時も、意識を失っている時も働いている深層意識がある。人間が造ったものは全て人間の心がからんでいる。日常生活は皆、心が作った物や社会のしくみによって、表面上は、より快適に便利になっている。しかし、それによって支配される。携帯電話、パソコン、インターネット等、今の通信技術には目を見張るものがある。携帯電話を忘れた時は不便ではあるが、目に見えない支配から解放される思いがある。
自動車、新幹線や飛行機も、残念なことに兵器もAIによって進化し人類を何度も消滅させる核兵器まで作ってしまった。とにかく心のたゆまぬ働きにより物質的には百年前には考えられない世界になった。特にAIの進歩は使い方次第では、人類に禍を与えかねない。
四苦八苦について前述したが、これらの苦しむ関係を、惑・業・苦と表現する。煩悩は我らを惑わし、業を作り苦しめる。苦の根本原因は何か。それは煩悩の働きであると仏教では説く。煩悩とは何かを、仏教ほど詳しく説く宗教はない(注1)。
なぜ苦しむかと言えば、神から与えられた原罪があるからと言う一神教もある。しかし、仏教は、自業自得を説く。仏教は全て自分の身口意の三業(三つの行為)のなせるわざであり、責任は自分にあると見る。
煩悩については、五位七十五法とか唯識の五位百法で詳しく述べている。煩悩の根源は我(自我意識)と我所(自分の所有欲)から来ている。自己中心の考えで他人のことを一切考えないことから生じる。典型的なものは貪・瞋・痴(無明)の三毒の煩悩である。これに、慢・疑を加え五大煩悩ともいう。『岩波仏教辞典(第三版)』によると、煩悩とは、
《身心を乱し悩ませる汚れた心的活動の総称。輪廻転生をもたらす業を引き起こすことによって、業と共に、衆生を苦しみに満ちた迷いの世界に繋ぎ止めておく原因となるものである。外面に現れた行為(業)よりは、むしろその動機となる内面の惑(煩悩)を重視するのが仏教の特徴であり、それゆえ伝統的な仏教における実践の主眼は、業そのものよりは煩悩を除くこと(断惑)に向けられている。》
唯識の学問では煩悩について詳しく述べているが、ともすると煩悩も概念化され、煩悩は死骸化されがちである。しかし、煩悩は現に生きる我々を苦しませている存在であることを忘れてはならない。
心を惑わし苦しめる原因となる煩悩の存在がわかったなら、それを消滅させる方法・修行が当然重視される。
釈尊の弟子達は七科三十七道品(注2)や六波羅蜜行(注3)を実践してきた。煩悩を断じてきた。煩悩を一つずつ断じ、最終的に全ての煩悩が消滅した時に悟りの世界に到達する。
七科三十七道品は原始仏教時代からの修行法である。段階的に煩悩を断じて最後に一切の煩悩を消滅させる。テーラワーダ仏教では今もこの修行法を実践しているが、成仏する為には、出家し、僧団生活するしかない。煩悩を断じる、消滅させることは云うは易しく成じ難しで、これは、いざ実践するとなると、なかなか思うようにいかない至難の業である。
なぜなら煩悩を退治しようとする心と、退治される煩悩も同じ自分の心だからである。自心の中で二つの心が闘うことになる。果たして、この矛盾した状態で解決するのであろうか。煩悩と悟りは対立するものであろうか。煩悩は煩悩、悟りは悟りと、まったく異なるものなのであろうか。そうなら煩悩は我と、無関係な敵である。
煩悩は悪への傾向と見る人もいるが、そんな単純なものではない。宿業(本能)とも云える深い心の働きである。煩悩は常に自分の心中にあり、自分を一番愛している。一番好きで、一番尊敬している。一番信じている。多くの人が自分を非難しても最後まで自分を擁護してくれる頼もしい心でもある。極言すれば煩悩なくして生きて行けない側面もある。子煩悩とはよく言った言葉である。
煩悩を断じようというのは私の心である。我の心が、我の心を断じようとするに等しい。煩悩を断じようとする心と、断じられる心も、どちらも我が心だから、断じようとすればするほど矛盾していく。
煩悩は自分を惑わすために、外部から来た悪玉みたいなものではなく、自心から生じたものである。でも実体はない。
盤珪禅師は、煩悩を止めようとするのは血を血で洗うようなもので、永久に血の汚れはとれないのだ、ということをおっしゃっている。
瞋り腹立の念が起るを止めうとなされて、それを留めますれば、二つの念が起りまして、走る者を追ふがごとくにござる。起る念と止めうと存ずる念が戦いひまして、永代止まぬ物でござる。尤も、先の血は落ちませうけれども、又後の血が付きまして、いつまでも、赤の色は退きませぬ。(盤珪禅師法語下/丸亀の巻)
その生じましたる迷ひの念を、見にくう思ひ、嫌ひまして、その念を止めようと思ひまして、止めに掛りますれば止め手と止めらるる物と二つになりまして、念を以て念止めましては、更に止まらぬ事でござる。譬へば、血を以て血を洗はんとするやうなものでござって、尤も始めの血は落ちましても、後の血で汚れますわいの。(盤珪禅師説法下)
釈尊が入滅されてから五百年近くなると大乗仏教が起った。
大乗仏教では「転迷開悟」という言葉が使われるようになった。迷いを転じて悟を開くという意味で、煩悩を断じるというより、煩悩というものをよく知ることによって煩悩の持つ力を、悟りを開く方向に転ずるという表現である。つまり、煩悩の本性を知ることが悟りであるということである。
この表現には煩悩を断じて悟りを得るという意味より、煩悩の本性を知ることが大事と言っている。もともと煩悩というものが存在して我々を惑わすのではなく、自分の欲が作った心であり、永遠不滅なものでなく縁によって偶々生じたもので、縁が変ればまた変化していく、実体の無いものである。この事実を知らしめるものが転じる力となる。自分が転じるなら、従来の、煩悩を断じるやり方と変わりなくなる。転ずるのは法の力・仏・如来の力によって転ぜられる。自分が転じるのではなく、如来によって転ぜられるのである。
このことを浄土教では本願力廻向と云い、密教では如来加持力という。如来を信じることにより加持力が働く。信じなければ、転ずる力にならない。これは「三密加持すれば速疾に顕わる」と同様に、如来三密加持したもうが故に即身に顕るのである。自分の力で自由自在に心を変えることができるなら、成仏に三大阿僧祇劫もかかることはあるまい。
空海が若い頃、悩まれたのは心と心の葛藤でいくなら成仏に三大阿僧祇劫かかるのは無理も無い。しかし如来の加持力により転ぜられるとなると、瞬時にして開悟に至ることを大師は覚られたのである。そうでないと、煩悩即菩提ということは実感を伴わない言葉の遊びにしかならない。
煩悩が仏智に照らされると迷いを翻し悟りに変る。問題の中に解答があるように、問いと答えは別々のものではない。衆生と如来の関係もしかり。衆生の自覚が仏智そのものである。
(了)
(注1)煩悩の呼称は、随眠・漏・取・縛・結・使・蓋・纏・垢とさまざまである。五位百法の心の分析では、主煩悩は、貪・瞋・癡・慢・疑・悪見の七つ。随煩悩は、忿(危害を加えんとする心)・恨(うらみ)・覆(自己の罪をごまかすこと)・悩(くよくよ悩んで周囲を悩ます)・嫉(嫉妬心)・慳(ものおしみ)・誑(たぶらかすこと)・諂(へつらうこと)・害(相手を傷つけること)・憍(うぬぼれ)・無慚(慚のないこと)・掉挙(そう状態)・惛沈(うつ状態)・不信(信のないこと)・懈怠(怠ける)・放逸(欲望のままにふるまうこと)・失念(記憶を失うこと)・散乱(心の集中を欠くこと)・不正知(誤った理解)の二十に分類されるが、これら以外にも組み合わせは無数にある。
(注2)六波羅蜜は菩薩に課せられた六種の実践徳目で六度ともいわれる。
①布施波羅蜜②持戒波羅蜜③忍辱波羅蜜(苦難に耐えること)④精進波羅蜜(たゆまず仏道を実践すること)⑤禅定波羅蜜(瞑想により精神を統一すること)⑥智慧波羅蜜(真理をみきわめ悟りを完成させる智慧)
(注3) 三十七道品 悟りの智慧を得る為の修行法のこと。
①四念住(四念処)
1、身→不浄と観じる
2、受→苦と観じる
3、心→無常と観じる
4、法→無我と観じる
②四正断(四正勤)……善・悪(不善)の行為・思考について
1、すでに起こっている悪は断ずる
2、いまだに起っていない悪は生じないように努める
3、いまだに起っていない善は起こるように努める
4、すでに起こった善は増大するように努める
③四神足(四如意足)……特に禅定(瞑想)について
1、欲神足……すぐれた瞑想を得ようとする
2、精進神足……すぐれた瞑想の為に努力する
3、心神足……すぐれた瞑想を得る為心を修める
4、思惟神足……思惟・観察してすぐれた瞑想を得ようとする
④五根……解脱に至るための能力・機根・美徳について(解脱に資する理念)
1、信根……信念の基礎
2、精進根(勤根)……精魂を込めてひたすら進む。勇敢に善の道を進むこと。
3、念根……記憶して忘れないこと
4、定根……心静かな瞑想。精神統一
5、慧根……清浄の法を増長させる力としての智慧
⑤五力……解脱に至るための具体的なすぐれたはたらき(解脱に資する実践)
1、信力
2、精進力(勤力)
3、念力
4、定力
5、慧力
⑥七等覚支(七覚力、七菩提分)…観察のための注意・方法
1、念覚支…おもいを平らかにする
2、択法覚支…智慧によって正しい教えを選びとる
3、精進覚支…一心に努力する
4、喜覚支…教えを実践する喜びを感じる
5、軽安覚支…心身を軽やかに快適にする
6、定覚支…精神を集中する
7、捨覚定…対象へのとらわれを捨てる
⑦八聖道支(八正道、聖八支道、八支聖道)…ブッダによって初めての説法の折に説かれたとされる
1、正見…正しい見解
2、正思惟…正しい考察・認識
3、正語…正しい言葉づかい
4、正業…正しい行ない
5、正命…正しい生活
6、正精進…正しい努力
7、正念…正しいおもい(記憶)
8、正定…正しい精神集中(精神統一)
以上の七種の修行法をまとめて七科三十七道品という。初期仏教経典における最も代表的な実践法。