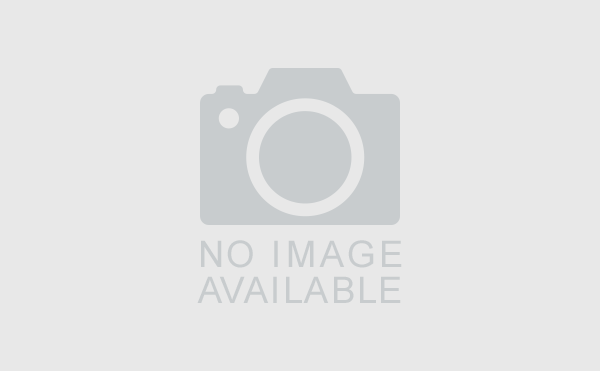なぜ観音菩薩は三十三身に変化するのか
五月に入り新緑が目にしみる候になった。四月は久しぶりに岡山で講習会を開いた。せっかく岡山まで行ったので、講習会の翌日、広島の宮島まで足をのばした。
宮島を訪れたのは、弟子の故坂野隆智師に特別な縁のある場所だからでもある。彼が宮島弥山にある求聞持堂で修行中(平成十八年)に行方不明となり、島中を捜索したが見つからず、その年の十二月頃、白骨で発見された。当時私はすぐお堂を管理している大聖院に詫びに行った。その日は、年末の行事がつまっていたので、彼が修行した弥山のお堂を見る暇もなかった。
宮島は下の方は、厳島神社、大聖院、大願寺等、神社仏閣が多い。
厳島神社の大鳥居はここしばらく覆いをかけられ大改修が行なわれていたのだが、今回訪れた時は、従来通りの堂々たる偉容を見せていた。
弥山は標高五三五メートルという結構高い山でケーブルを乗り継いで登った。ケーブルを下りればすぐ頂上だと思ったが、弥山頂上まで徒歩三十分とあったので、家内と一緒にせっかくここまできた以上、登らずには帰れまいと歩き出したはいいが、山登りの格好でなく、革靴でネクタイ、ワイシャツの背広姿で杖を突きながら登ったので、持病の腰痛もあり、かなりきつかった。その日は好天で観光客が多かった。八割方は外国人だったが、彼らは慣れたもので、スニーカー、半袖の軽快ないでたちで、我々を次々追い越して行った。
しかし坂野師の供養を兼ねていたので登り続けた。これが最後の登山かもしれないが、きつい山登りも終わってみれば何か達成感があった。
山頂は獅子岩など巨石が直立し、展望台からの三百六十度の見晴らしはすばらしかった。頂上の下方には弥山の本堂や、弘法大師が灯した消えずの灯の霊火堂があった。虚空蔵求聞持法は百日間、毎日虚空蔵菩薩の真言をひたすら念誦するシンプルな行である。独りで修行するので精神状態が不安定になる人も多いといわれているが、彼がどうして御堂から出て行方不明になったのか。事故で崖から転落したのか等、理由も不明である。今回実際に登ってみて、弥山は樹木が生い茂るかなり深い山で、すぐに見つからなかったのも無理がないと思った。
尊い目標に向かっての修行中の事故である。坂野師にとっては目的に達する途中での、残念な結果になった。しかし、彼の求道精神はそこで消滅したわけでなく、道を求める人に、今も連綿と受け継がれていると信じている。玄奘三蔵に代表されるように、漢土からインドに、命がけで求法された僧侶もたくさんおられ、途中の砂漠や海中に没せられた方も少なくない。このような無数の真摯な求道者たちがあってこそ仏法は受け継がれてきたのである。坂野師の求道心にあらためて合掌した。
さて、五月十八日は正五九の観音会に当り、会員と共に観音経を読誦した。普段は読まない長行から偈文に至る全段を読んだ。その後の法話では、偈文には出てこないが、観世音菩薩が三十三身に変化するという箇所を取り上げて話した。
観音様が三十三身に変化するということはよく知られており、これに因んで三十三カ所の観音霊場をめぐる。小院も江戸三十三観音の第十八番札所になっている。札所の寺はもちろん観音様が本尊であるが、三十三に変化したお姿を全て祀っている寺は少ない。以前、仁和寺の観音堂を参拝した時は本尊様の両側に三十三身の像がずらりと並んでいたし、回廊の壁にも観音菩薩にちなんだ図が全面に描かれていた。観音様は、上は仏から、梵王、帝釈天等の神々、いろんな業種の人間、子供、そして人間だけでなく鬼神の類も網羅している。三十三で一切衆生を表現している。
この三十三身に変化して衆生を救う観音様の慈悲心はわかっていたが、その深い意味はよくわからなかった。令和五年の「多聞」五月号(五五二号)の巻頭言に「仏が人間になる道」というタイトルで、成仏への道は二つあることを書いた。「人間が修行して仏になる道」と、「仏が修行して人間になる道」である。参照していただきたい。
釈尊以後のお弟子さんたちは、目の前にまします釈尊という仏陀を目指して修行された。後に七科三十七道品(「多聞」五七五号「転迷開悟」)という修行課程も完備し、羅漢さんたちは、この修行法に従っていけば仏陀になれると信じ煩悩を断じて行かれた。しかし、この道は出家にならなければ成就されない狭い道である。二百五十戒を守り、僧団生活ができる人々でなければ、道を成就するのは不可能に近い。
しかし、釈尊入滅後、五百年も経過すると、僧侶の中からも仏陀は釈尊独りではないという考えが生まれてきた。釈尊が仏陀となられたのは「法」を悟ったからである。この「法」には種々の意味があるが、仏教で法というのは、まず仏陀の教えを云う。真理といわれるものは不変にして普遍なる真実の道を説いているのが仏陀の教説だからである。真理は過去・現在・未来を通じて変わらない道理である。この法を悟られたのが釈尊であることから仏教は釈尊から始まったといわれる。しかし、釈尊が悟られた法は釈尊以前からあるし、現在・未来にわたって不変であり、普遍的な真実の道理である。そして法には我々衆生をして悟らしめる力がある。真実には力がある。
科学でも真理は云うが、科学でいう真理には我々を悟らしめる力があるとは云わない、あくまでも真理を追求するのは科学者であり、真理は動かない。それを認知し取り出すのは人間の理性であるという。故に、取り出された真理・法則は人間の思惑で善にも悪にも利用される。そういう意味では人間が真理を動かせる、利用できると思っている。
仏教で云う真実の道理と共通する面は過去・現在・未来を通して変わらない原理・法則である。大乗仏教が生まれるまでは、仏陀に成ることを求めて修行するが、法はじっとして動かない、不動の存在である。人間がそれを求めて修行する。故に小乗仏教(南伝仏教)では仏と言えば釈尊しか認めない。仏像と云っても皆、釈迦牟尼仏である。立像・坐像・涅槃像のいずれかである。大乗仏教のように、大日如来、阿弥陀如来・薬師如来や観音菩薩・普賢菩薩・文殊菩薩・地蔵菩薩等、たくさんの仏・菩薩は生まれてこない。なぜなら釈尊にして初めて法(真実の道理)の世界を覚ったからである。この場合、法は動かず釈尊の成道を以って初めて法の世界が顕わになったからである。しかし、果たして法は一切働らかず、釈尊は、自身の修行の力のみで悟ったのであろうが、法には釈尊を悟りに導く力がなかったのだろうか。この点については、私は法の力によって釈尊も最終的な悟りに至ったのではなかろうかと思っている。
釈尊が成道した後に語った話がある。「私が、ある時、古人が歩いたと思われる古い道を見つけ、その古道に沿って歩いていくと眼前に大きな城(宮殿)が現れた」という話である。
その言葉から見ると釈尊が古人の道を見つけ歩んだ結果、眼前に大きな城が現れたと見られるが、半面、古い道を目にして釈尊がそれに導かれていくと果たして思いかけず眼前に捜し求めていた城(法)が向こうの方から開けてきたともとれる。動かない筈の真理は目には見えないが、求める者の願いに応じて自覚という形で目の前に現れたとも取れる。もちろん真理が変化することはないが、不動にして動という表現がこのことを表わしている。仏教では、体相用という。体は本体、相はすがた、用はその働きである。不動而動とは用(はたらき)である。
釈尊が成道した仏陀伽耶には最初に悟りを開いた場所から、更に数カ所、二番の禅定、 三番の禅定から、七つの禅定の聖地がある。覚りの後の七週間と七つのチェーティヤ(聖なる場所)つまり更に瞑想するに従って、悟りが深まっていったことを示した事跡である。仏陀伽耶にお参りすると必ず案内される。
これは何を示しているのか。恐れ多いことであるが、釈尊の悟りが、個人的悟りから、一切衆生を救う公的、平等の悟りに法が導いたのではないかと私は思う。
故に大乗仏教になると、法から数多くの仏・菩薩が誕生してくる。法という抽象的なものから、具体的に法身という仏が生まれてきた。この場合、仏陀を如来と表現した方がわかりやすい。「如」つまり法より来生する。漢民族は、法(ダルマ)を「如」という漢字で一如・真如・如如・法如などと表現した。
法というと不可称・不可説・心滅言断・言語道断の世界であり、敢えて表現すると如虚空・無限・無碍、清浄や光としか言いようがなく、これでは、われらは法(真実の道理)を具体的に覚ることができない。
迷い苦しむ我ら衆生を見て、法が大慈悲心を発し、先ず法身仏として顕れ、更に具体的な応身仏、報身仏(菩薩の時、将来仏に成ったら、このようにして救いたいと本願を建て、その願に報いて顕れた仏)となった。阿弥陀仏や薬師如来に代表されるように、法身大日如来以外の仏はみな報身仏である。応身仏は人間の姿になって現れた仏、つまり釈迦牟尼仏のことである。詳しくは胎蔵界曼荼羅に描かれている。中央の大日如来から、四仏(宝幢・開敷華王・無量寿・天鼓雷音)、四菩薩(普賢・文殊・観自在・弥勒)、願意を同じくする諸院の菩薩、そして当時のインドの神々も外枠に位置づけられている。
このように仏・菩薩様のこの世に現れた経緯を知ることにより、如来や菩薩は我らを救う為に法から具体的に人間の姿をとって現れた姿であることがわかる。つまり法が仏・菩薩という人間の姿になって、現に今、救済活動をしておられるのである。
観音菩薩は、人間はもちろん、帝釈天・大自在天・毘沙門天・天竜八部をも救う為には具体的に彼らの姿をとって顕われる。
なぜ仏・菩薩が迷える我らを哀れんで助けるのか。哀れむ前に仏は我らの本性(仏性)を信じているからである。我々は気づいていないが、我々には生まれつき仏性が具わっていることを仏は深く知り信じている。だから、救わなければならないと責任を感じられ立ち上がる。必ず救うという大慈悲心が湧いてくるのである。半端な憐れみではない本気の慈悲心である。単なる哀れみではない。どの仏様も菩薩様も皆この大慈悲心を持って我らに対応している。
密教ではこの大慈悲心を加持力という。加持力の無い仏・菩薩はおられない。必ず加持力を具えておられる。大師も「加は如来の大悲を表わし、持は衆生の信心を表わす」(即身成仏義)と明記しておられる。
三十三身のうち、我々は長者身・居士身・宰官身・比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷身・婦女身・童男・童女身のどれかに該当する。もっと具体的に云えば、観音様は、他でもないこの私自身になって説法して下さる。我らが仏・菩薩に成るのは至難の業だが、仏・菩薩が人間や神々になるのは、たやすいことである。一応、三十三身に変化すると説いているが、もっと端的に言えば、この世でたった一人しかいない自分自身になって説法して下さる。だから頭が自然に下がるのである。感謝しきれない大慈悲心である。このことを信じると不思議にも仏・菩薩の、我らを信じ救わずにはおられないという大慈悲心が身にしみて感じるのである。これを同体大悲という。
更に、この仏・菩薩は大慈悲心を真言という短い言葉につめられ我らに与えられた。
真言は仏・菩薩が我等衆生を救う願いが込められた祈りの言葉である。真言には仏・菩薩の内容である真実、真理がつまっている。真実には迷いを開く力がある。『般若心経秘鍵』に「真言は不思議なり、観誦すれば無明を除く、一字に千理を含み、即身に法如を証す」とある。故に我らが真言を誦える時、即真言に具わっている加持力が働くのである。
『観音経』は、くり返し、困っている時はいつでも「南無観世音菩薩」と称えなさいと述べている。「南無観世音菩薩」と称えると即座に、そのとなえる人の姿となって現われる。つまり自分自身になって下さる。観音様の姿を想ってもいいが、もっと具体的で直接的なのは「音声」である。真言である、真言は私が誦えているが、同時に観音様も誦えている。オンは我らの領分、アロリキャソワカは観音菩薩の領分で、わが名を呼ぶものは必ず救うぞという意味である。我と菩薩が一体であることを示す祈りの言葉であり、そこには加持力が働らいている。
観音経が編纂された頃は、未だ密教が漢土に伝わっていないのでただ「南無観世音菩薩」ととなえなさいと表現しているが、これは、密教でいえば、オンアロリキャソワカ(聖観音)やオンマカキャロニキャソワカ(十一面観音)という真言になる。
真言は、意味を訳さず、必ずインドのサンスクリット(梵語)で発音するきまりになっている。「南無観世音菩薩」の南無と菩薩は梵語の音写だが観世音は漢訳された言葉なので厳密には真言とはいえない。しかし言わんとするところは正しく真言と同じである。
釈尊といえども時代の制約があり、当時、直接、大乗仏教や密教を云うことはできなかった。しかし、釈尊の発言は真言と云ってさしつかえないと思う。なぜなら法という真実の道理を直接説いたからである。
ということは、密教は何も七世紀ごろに出現した法門ではないことを示している。密教はもっと以前からある。以前どころか密教は、釈尊が法を発見した以前からあるところの仏教だと私は思っている。