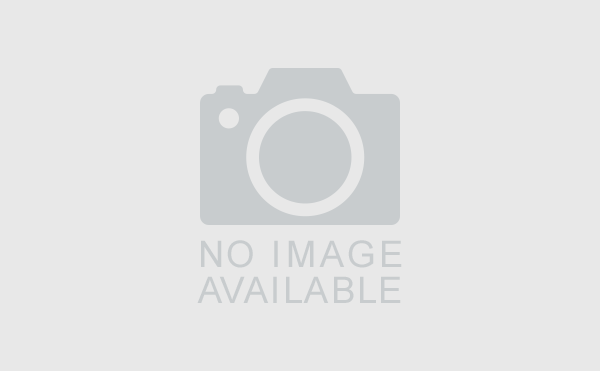如来が菩薩になり、菩薩が私になって下さる
織田隆深
昨年、昭和大仏四十周年法要後の挨拶の中で、私はこういうことを話した。
「昭和大仏は奈良大仏、鎌倉大仏と同じように見えるかもしれないが、よくよく見て下さい。昭和大仏は詳しく云えば、大日如来を表現した大仏である。先ず、五智の宝冠を頂き、瓔珞、臂釧、腕釧で身を飾り、高級な薄絹の衣類を着ている。また、冠の中は長い髪を高く結って冠の下は髪を結っているし、両耳からは髪の一部が垂れている。奈良大仏、鎌倉大仏のような出家の姿ではなく、われわれと同じ在家の姿なのです」と。
普通は釈迦如来のように、頭はパンチパーマのように見えるが、これは螺髪(注)といい、一つ一つ髪を小さくくるくる巻いたもの。仏様は人間の姿をとっている。仏様には、「三十二相八十種好」と称し、一般人と異なる身体的特徴があり、その一つが螺髪である。また、頂上肉髻相といって、頭の頂上が隆起していたり、白毫といい、眉間に白い毛が渦巻状に生えて、そこから光を放つとか、一人でも多くの衆生を救う為、指と指の間には膜がある(縵網相)とか、人間の姿をとってはいるが、よく見ると数多くの違いがあることがわかる。
顕教では、菩薩の数は密教に比べると少ない。観音菩薩、勢至菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩ぐらいである。それに比して密教のマンダラに描かれている菩薩はかなりある。その菩薩の姿は剃髪した地蔵菩薩を除くと、ほとんど在家の姿である。
前述したように、昭和大仏(大日如来)は有髪で冠をかぶったり、薄絹を纏いつけた数々の装身具を纏った在家の姿である。つまり、出家ではなく、我々衆生と等しいお姿である。胎蔵界マンダラの中央の大日如来を東西南北を囲む四仏(阿閦・宝生・無量寿・不空成就)は皆、僧形で頭は螺髪で簡素な衣を纏った出家の姿である。しかし、その囲りの菩薩は全て有髪で、装身具を身に着け薄絹を纏った、インドの裕福な在家の姿である。
大乗仏教が生まれる紀元前後の、修行者は羅漢さんに代表されるように剃髪し皆糞掃衣を着た出家の姿であり、有髪で装身具や高級な絹織物を着た羅漢さんは一人もいない。
大乗仏教になると修行者である羅漢の呼称ではなく菩薩と呼ばれる。菩薩には顕教と密教の菩薩がある。顕教の菩薩は、将来、正覚を得ることは間違いないが、将来正覚を得たら、このように衆生を救いたいと本願を発している修行中の出家である。
一方の密教の菩薩はまだ覚っていない修行中の行者ではなく、已に正覚を得た如来(仏)が、衆生を救う為にわれらと同じ人間の姿を取って、法(覚り・如来)の世界からやってきた。如来より更に具体的に因の位(衆生)に降りて、我々衆生と同じ心と身体を以って、慈悲の働きをされているお姿である。
如来(仏)の悟りは、果の位である。如来の存在は、煩悩多き我らには、眩しい光のようなものなので、直接見ることはできない。そこで光を和らげ、煩悩に苦しむ我らの中に入ってきた。道教では娑婆世界に生きる仙人のことを「和光同塵」という。そのように如来が光を和らげ、我らと同じ姿になられて、つまり如来が菩薩の姿になって、更に具体的に我々の煩悩の中に入って来られた。
だから菩薩は我らと同じ目線で救済される。このように、修行者の呼称も小乗(出家しか成仏できない教え)の修行者は羅漢と呼ばれ、大乗(僧俗共に成仏できる)になると菩薩と呼ばれる。
大乗の菩薩の二大特徴は「上求菩提・下化衆生」のように自ら悟りを求めると同時に、迷える衆生を救わなければならない。
同じ菩薩でも、密教が現れるまでの菩薩は未だ覚っていない修行者の意味が強いが、もしそうなら、衆生を救うことはできない。衆生を一人も救えないなら菩薩と云えないという矛盾が出て来る。
ここをはっきりさせたのが密教の菩薩である。密教の菩薩は已に覚った如来が迷える衆生を見て、何とか救われなければならないと人間の姿を取った。
この菩薩は、一切衆生を救わなければ成仏しないという誓願(五大願・四弘誓願)を建てられた。この誓願は本来なら、我々が発さなければならないものである。それを菩薩が我らに代って発された。もはやこの誓願が成就しようが成就しまいが、我々の為に発して下さったことが重要なのである。われらは素直に伏して戴くばかりである。
煩悩多き身であるが、菩薩が我らに仏性があることを信じて発された誓願に感謝し、真言念誦する生活を実行することが我らの務めである。
如来が菩薩になり、更に菩薩が私になって下さる。この菩薩の同体大悲の心を我々がいただくと、菩薩の誓願が私ども心身に満ち満ちてくるのである。オンアビラウンケンのオンは菩薩が我になって一緒に大日如来に感謝する帰依の信心であり、即大日如来、それに応じて、我となって救って下さる。
我々は普段仏像や菩薩像を前に拝んでいるが、如来像や菩薩像には深い意味内容があることを知ってほしい。
今年に入ってから、何度も繰り返し、人間が仏になる道(従因向果)と、仏が人間になる道(従果向因)について述べてきたが、前者の道は出家しなければ、とても成就できない、険しい狭い道である。
これに対し後者の道は、仏が、我の立場と深く知らしめし、色も形もない虚空の如き、法の世界から具体的に我と同じ煩悩に悩む多くの衆生を救うため在俗の姿を取り、煩悩に染まっている我等を本気で救済せんとする大道である。菩薩道も従因向果の、我らと同じ心身になって救って下さる従果向因の二つの道があることを深く知ってもらいたい。
従果向因には如来加持力が働いている。だから従因向果も如来の加持があってこそ成就する。
菩薩は煩悩界に入っても染まらない。あたかも蓮華が泥沼にしか花を咲かせないように娑婆の汚泥に染まらず、煩悩に染まっている我を救って下さる。
このことは、仏像を見るとよく分かる。
どの仏様も菩薩様も、蓮華の台座に坐るか立っておられる。天部の諸天は荷葉に坐しておられる。
顕教では、我と仏の関係は二而不二であると説く。究極的には仏と衆生は同体であるが、現実世界に於いては仏と我の位は判然としなければならない。
密教では仏と衆生の関係は六大無碍で表現する。仏も六大、我も六大と見るので、表面上の分限は明確にしなければならないが、内面の世界では「即身に法如を証す」の如く加持が働くので、成仏は遥か彼方にあるのではない、汝自身を如実に知る所にあると「即身成仏」を如来が云っておられるのであれば、ありがとうございますと感謝し、もったいないことですと、成仏をお返しすればよい。何も即身成仏だからと云って成仏を自慢することはない。
オンアビラウンケンと感謝すると、功徳は如来に帰っていく。帰ることで逆に功徳は我が身に遍満するのである。
(注)仏、菩薩の髪型は、大きく分けて「螺髪」と「髻」の二種類がある。螺髪は、如来に特徴的な巻貝のように渦巻状になった髪型で、悟りを開いたことを表わす。鎌倉大仏や奈良大仏も螺髪である。五劫思惟阿弥陀仏のように、螺髪がつみ重ねたような独特な髪型もある。髻は髪を束ねて結い上げる髪型だが、菩薩や明王(炎髪)・怒髪・弁髪等)に多い。単髻、双髻、五髻・高垂髻・垂髪など様々な結い方がある。